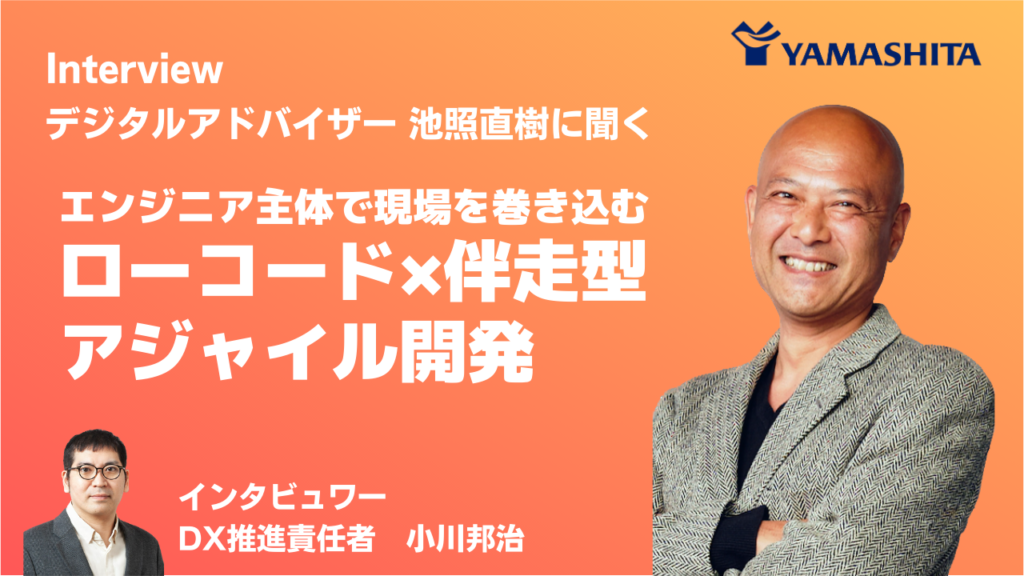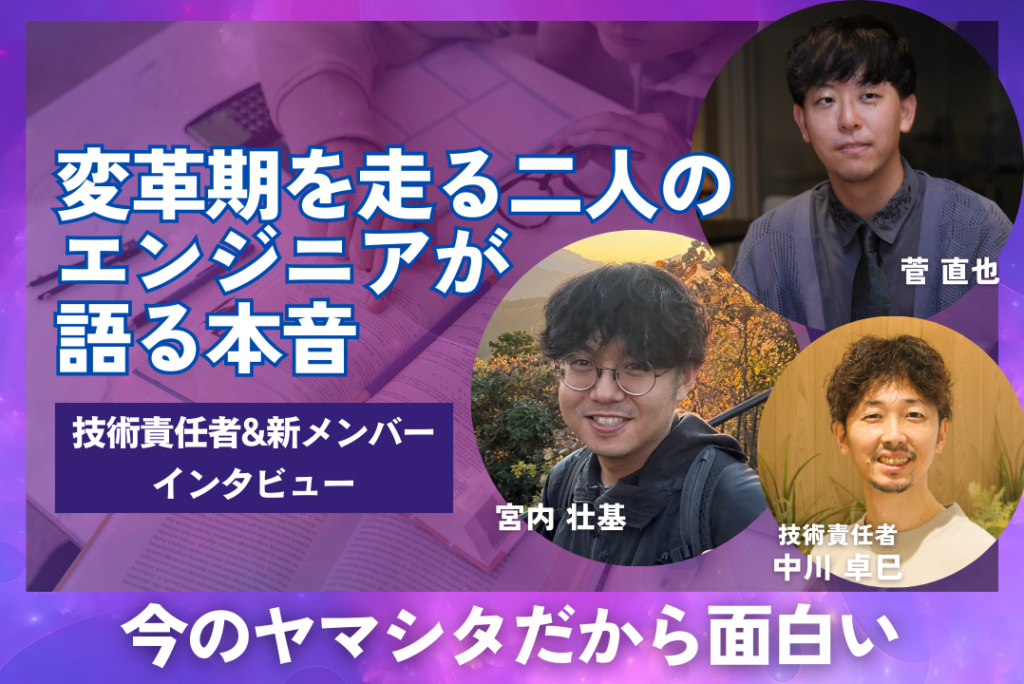
Release:2025.08.22 Update:2025.09.11
2025年春、ヤマシタのシステム開発部に2人の新メンバーが加わりました。
創業60年以上、介護用品レンタル・リネンサプライ領域で安定した事業基盤を持つヤマシタ。しかし、今その中核である基幹システムやCRM(顧客管理)の分野は、まさに変革の真っただ中にあります。
そんなタイミングで入社したのは、豊富な経験を持ちながら「まだ成長したい」と挑戦を選んだ菅さんと宮内さん。
技術責任者の中川が司会となり、2人のこれまでのキャリア、ヤマシタに飛び込んだ理由、入社後のリアルな印象、そしてこれから描く未来について、本音で語ってもらいました。

中川:まずは簡単に自己紹介をお願いします。
菅:前職の株式会社BuySell Technologiesでは、エンジニアリングマネージャーとして約10名のチームをマネジメントしながら、インフラ・フロントエンド・バックエンドなど幅広い技術領域をフルサイクルで経験してきました。採用や評価、技術イベントへの登壇なども担当していましたね。事業としては、リユース品の出張買取を行っている会社で、買取から販売まで一気通貫してデータを管理・活用するプラットフォームシステムの開発を行っていました。買取申し込みから査定、在庫管理、販売までをまるっとプラットフォーム化する開発に携わったのは大きな経験です。
宮内:私は直近、SREホールディングス株式会社や株式会社アンドパッドに所属し、新規性の高い領域でのシステム開発に携わってきました。特にここ4〜5年は、新規事業の立ち上げを経験してきたことが大きな特徴です。新規事業はチーム体制や開発プロセスが整っていないことも多いため、チーム環境の整備や仕組みづくりを行いながら開発を進めてきました。
また、いわゆるテックリード的な役割として、誰も拾えていない課題を解決したり、組織全体に導入するソフトウェアを選定したりと、チームにとどまらず組織横断で動くことも多くありました。
中川:お二人とも、コードを書くことだけでなく、組織やプロセスにも関わってきた経験があるのは心強いですね。

中川:数ある会社の中で、なぜヤマシタを選んだのでしょうか?
宮内:理由は大きく2つあります。1つ目は“タイミング”です。ヤマシタの開発組織はまだ立ち上げ段階にあり、これからカルチャーやプロセスをつくっていける段階です。数年後には開発体制が固まり、新しい提案をする余地が少なくなるかもしれませんが、今なら自分のアイデアをダイレクトに反映できる。その自由度の高さに強く惹かれました。
2つ目は事業そのものの魅力です。直近のキャリアではSaaS開発が中心で、次第に「地に足のついた事業で、利用者から直接フィードバックを得ながら開発したい」と思うようになりました。ヤマシタは介護・福祉という社会的意義の大きい領域で、事業の手応えをダイレクトに感じられる点が非常に魅力的だと感じました。
菅:前職でキャリアを整理していたとき、「事業への貢献度が高い技術職として、もう一度地に足をつけて組織と向き合いたい」と考えていました。そんなとき出会ったのがヤマシタです。介護・福祉の現場を支える堅実で社会性の高い事業でありながら、技術面で伸びしろがあり、前職と業務フローや顧客層に共通点もありました。
また、上長と相談しながらJD(ジョブディスクリプション)を柔軟に決められる裁量や、AI活用を積極的に進める文化も魅力でした。最終的な決め手は、EM(エンジニアリングマネージャー)としての経験を評価されたうえで「まずはIC(個人貢献者)として技術に集中してほしい」と言っていただけたことです。私はマネジメントも開発も両方好きな“欲張りなタイプ”で、転職先ではまずICとして入社し、技術と向き合いながら、将来的にはマネジメントも含め幅広く関わりたいと考えていました。自分の意思を尊重してくれる姿勢に信頼を感じ、「ここなら長く本気でやれる」と確信しました。

中川:入社後の印象はいかがですか?
菅:現場の温度感を大切にしつつ、業務効率化や改善に本気で取り組む姿勢が印象的でした。例えば技術負債の解消や業務効率化に取り組む際、ボトムアップで提案すると対話を通じて最適な方針を決める、といった形で現場の意見を尊重してくれます。業務上の課題もボトムアップで改善につなげられる点は、働きやすさに直結しています。
また、入社前は少し硬直的な雰囲気を想像していましたが、チームは穏やかで対話を重視しており、リモート主体でもHuddleや雑談を通じて程よい距離感でコミュニケーションが取れます。さらに、経営幹部や他部門の社員とシステム開発部門がフラットな関係を築いており、自由度高く取り組めます。
宮内:入社して特に印象的だったのは、現場の自由度の高さと経営陣との距離の近さです。ルールや型はまだ少ないですが、逆にその分「ヤマシタにとってあるべき開発組織は何か」を考え、直接フィードバックできる余地が大きく、役職やタイトルに関わらず個人の実力が反映される環境です。経営陣も若くフラットで、現場の声を大事にしている点には驚きました。非上場で社員が約3000名の規模ながら、経営幹部ともカジュアルに話せ、意見をしっかり聞いてくれる機会があります。人財を会社の「財産」として大切にする姿勢を、経営ボード自らが日々のコミュニケーションで体現している点にも強く感銘を受けました。
また、オンラインミーティングではカメラをオンにする方が多く、非言語的なコミュニケーションにも配慮されていると感じます。

中川:現在のプロジェクトは?
菅:現在取り組んでいるプロジェクトは、非常に大規模な介護用品レンタル事業における基幹システムのリプレイスです。単に実装するだけでなく、今後5〜10年使える設計を目指して、設計手順や開発プロセス、詳細設計などあらゆる面で工夫を重ねています。入社直後からこうした大規模プロジェクトに関わることに挑戦しがいを感じながら取り組めています。私のような難しい課題に挑戦したい人や、自分の知識・スキルを広げたい人には非常に魅力的な環境です。
宮内:私も菅さんと共に、基幹システムのリプレイスを担当しています。現在は既存システムの解析調査と計画立案を生成AIをフル活用しながら非常に少人数の体制で行っています。AIをフル活用しながらではありますが、既存システムを読解する力も求められます。例えるなら、古いシステムをモダンに書き換えていく作業で、古典を現代語に訳すような感覚です。
昨今、AIによる開発支援環境が非常に向上しているこのタイミングだからこそ、この少人数で、数百億の売り上げの根幹となるシステムの解析にチャレンジできるという意味では、地味で泥臭い部分もありますが、他社では経験ができない挑戦的な仕事です。

中川:これから入社する人へのメッセージは?
菅:ヤマシタは、地に足をつけて事業と向き合いながら技術を活かしたいエンジニアに向いている職場だと思います。開発部門と現場の距離が近く、現場の課題や反応を直接感じられます。社内向けシステムの内製開発ですが、どうやったら組織を良くできるか、プロダクトにより価値を感じてもらえるか、本気で取り組めます。会社としてはしっかりした基盤がありますが、変化を受け入れる柔軟さもあり、派手な技術トレンドだけでなく、現場の声に応える地道な改善を楽しめる方に来てほしいですね。
また、決まったレールを走るのが好きではなく、「もっとこうしたらいいのに」と考えて行動できる人にとっても、とても楽しめる環境です。0→1フェーズが好きで、「自分がルールを作る」という意思を持ち、ある意味カオスを楽しめる方と一緒に働きたいですね。
宮内:当社の開発チームでは、エンジニア自身が現場の方々と直接コミュニケーションを取り、課題を調査・理解しながらシステム開発に取り組むことができます。現場の非エンジニア人財もノーコード・ローコードを活用した社内アプリ開発やハッカソンなどに取り組んでおり、デジタルをフル活用するという風土が醸成されています。
そのため、単なるソフトウェア開発にとどまらず、抽象的な課題解決や現場の価値を創出することに関心のある方には、非常に相性の良い環境です。
技術面では、Devin、Cursor、GitHub Copilot、Claude Codeなどの開発支援AIツールをはじめ、先端的な技術を利用できる環境が整っています。これらのツールを活用し、効率化や省力化を積極的に推進できるのも当社ならではの魅力です。
リネンや介護用品レンタルの事業領域からは意外に思われるかもしれませんが、社内の足回りの軽さと開発者が挑戦できる環境は、入社後に必ず魅力を実感できる部分です。
中川:新しい仲間をお待ちしています!
編集後記
「型がない=課題が多い」ではなく、「型がない=自由に作れる」。
2人の話を聞いて、ヤマシタの開発組織がこれからどんな形になっていくのか楽しみになりました。
成長フェーズに飛び込みたい方は、ぜひエントリーしてください。